
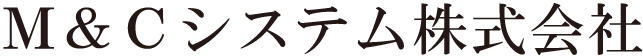
社員紹介

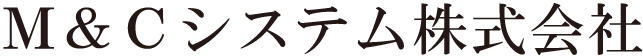
社員紹介
付加価値 × 好奇心 × 時間効率
R・M/2024年入社
流通科学大学 経済学部
■求められるエンジニアとは
就職活動の際、職業調査をする中で『エンジニアは名指しで指名を受けることがある』ことを知り、どうやったらそんなエンジニアになれるのかを考えるようになりました。面接時、担当者から「将来どのようなエンジニアになりたいか?」と聞かれた際は「自分に指名が来るほどのエンジニアになりたいです」と答え、その際に「会社の内外かかわらず評価を受ける必要があるね」と返答されたことを今でも覚えています。 "評価を受ける"というのはどういったことなのか。 プログラミング等の技術的な要素はもちろん、指示を受けた業務を着実にこなすことだけではなく、人間力(この人と働きたいと思ってもらえるかどうか)も大切な要素です。 そして、そこに加えてなにかプラスαの価値を創造していくエンジニアが"評価されていくエンジニア"であると私は考えています。今後も積極的に学習を積み重ね、「自分に指名が来るほどのエンジニア」を目指していきます。





■努力の中で感じた事
入社後の3か月間(4~6月)は外部研修に参加し、プログラミングの基礎から実践的な開発演習を学びました。わからない所があれば同じ研修会場の受講生同士で教えあって解決したり、研修用PCを持ち帰って与えられた課題の復習を行う等、技術の習得に奮闘する日々でした。これらの努力を通して、SQL操作やJavaなどプログラミングスキルと報告書(日報)の記述や口頭での報告の仕方など社会人としてのスキルを鍛えることができました。 また、研修期間中には加えて自主学習も行うことで学習を習慣化し、実務を行っている今も継続しています。私にとってこの研修期間は講師(サポーター)や向上心の強い受講生が周りにいる恵まれた環境の中で過ごすことができたと感じています。良い環境を活かしていけるかどうかはやる気次第です。 研修期間にどれだけのことを吸収できるか人それぞれ差はありますが、努力すればした分だけ後々の自信につながってくると思います。

■"急がば回れ"も対策の一つ
現在はVBAを用いて、業務ツールを開発するプロジェクトに参画しています。 研修で学んだJavaなど他のプログラミング言語と条件分岐や配列などの基本的な考え方は同じでも変数宣言の仕方や記述方法が異なる為、初めはわからないことだらけでした。そのため、自分なりに調べて理解をすることやVBAに詳しい社員を捕まえて質問し、疑問点や課題の解決を行っています。 おそらく今後も業務を行う中でこういった場面に直面するかと思います。対策として質問するもよし、調べるもよし、Chat GPTに聞いてみるもよしですが、すぐに解決できるスキルを持っている人、常にどうすれば解決できるか考えられる人はIT業界に向いていると思います。当たり前ですが仕事は一つひとつのタスクに期限があり、期限厳守の世界です。一人で解決しようと悩み続けることは経験として無駄にはならないですが、時間は有限であることを考えるとそればかりをやるのは得策ではありません。 回り道に見えるかもしれませんが、少し調べて解らなければアドバイスを求めたり、意見交換をしたりして社員やチームとコミュニケーションを行うことも視野に入れるべきです。時間を効率よく使うためにはどういった解決方法を選択していくかを考えることも業務に取り組む姿勢として求められます。